【令和5年4月~】雇用保険料率の公表
2023/02/13
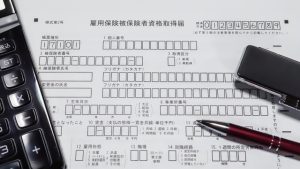
厚生労働省のサイトにて、例年より早く令和5年度(2023年度)の雇用保険料率が公表されました。現在1.35%の雇用保険料率が、2023年4月から1.55%に引き上げられることになります。
https://www.mhlw.go.jp/content/001050206.pdf
雇用保険料率については、2022年に2段階引き上げられたばかりです。
特に2022年10月1日より0.95%から1.35%に引き上げられたことは、引上げ率が大きかったこともあり、皆さんも記憶に新しいかと思います。
では、なぜ今回さらに雇用保険料率が引き上げられたのでしょうか。
雇用保険料率の引き上げの理由、また、企業や労働者に与える影響などについて解説していきます。
- 【令和5年4月~】雇用保険料率の変化
冒頭では、2023年4月より1.55%になるとご紹介しましたが、これはあくまで一般の業種に該当する方の話です。雇用保険料率といっても、実はすべての使用者が同じ料率で保険料を支払っているわけではなく、事業の種類によって保険料率は異なります。
雇用保険料率は、以下のように3つの業種に分けて算定されます。
令和4年度(10月~)料率 → 令和5年度 料率 (100分の1)
|
|
従業員負担 |
会社負担 |
合計 |
|
一般の事業 |
0.5%→0.6% |
0.85%→0.95% |
1.35%→1.55% |
|
農林水産・清酒製造の事業 |
0.6%→0.7% |
0.95%→1.05% |
1.55%→1.75% |
|
建設の事業 |
0.6%→0.7% |
1.05%→1.15% |
1.65%→1.85% |
ここでいう一般とは、農林水産・清酒製造、建設の事業以外のすべての業種を表します。
そのため、多くの企業は一般の業種に該当します。
農林水産・清酒製造の事業や建設の事業の雇用保険料率が高く設定されている理由としては、「就業状態が不安定になる可能性が高いこと」が挙げられます。就業状態が不安定になりやすいということは、失業手当を受給する可能性が高いということです。
農林水産業・清酒製造の事業には、季節によって仕事が途絶えてしまう期間が出てきてしまうが人がいたり、建設の事業では現場ごとに雇用契約を結ぶケースも多く、雇用契約を結んでいない期間中に失業手当を受ける可能性が考えられます。
一般的な生命保険でも、持病を思っている人は保険金を受け取る可能性が高いため、保険料が高めに設定されているケースが多いのと同様に、手当を受ける可能性が高い業種では雇用保険料率が引き上げられています。
建設の事業の雇用保険料率がさらに高い理由としては「助成金の支給が多い」ことも挙げられます。助成金の財源は、使用者が支払っている雇用保険料です。助成金はどの業種でも用意されていますが、建設業は一般的な助成金に加えて独自の助成金の種類がとくに多いため、保険料率が上乗せされているのです。
ほかの就業者と公平性を保つためにも、業種によって保険料を調整することは必要な措置となっています。
- なぜ雇用保険料率は引きあがったのか?
雇用保険料率は、物価や失業率などさまざまな要因を考慮し、定期的に見直しが行われていますが、今回の引き上げの最も大きな原因は新型コロナウイルス感染拡大とその長期化にあると考えられています。
そもそも雇用保険料率は、下記のとおり、新型コロナウイルス感染拡大前の積立金に余裕があったときに、暫定的に引き下げられていました。
|
平成22年 |
1.55% |
|
平成23年 |
1.55% |
|
平成24年 |
1.35% |
|
平成25年 |
1.35% |
|
平成26年 |
1.35% |
|
平成27年 |
1.35% |
|
平成28年 |
1.1% |
|
平成29年 |
0.9% |
|
平成30年 |
0.9% |
|
令和元年 |
0.9% |
|
令和2年 |
0.9% |
|
令和3年 |
0.9% |
|
令和4年(4月) |
0.95% |
|
令和4年(10月) |
1.35% |
しかし、新型コロナ感染拡大により、積立金が激減してしまったため、それまで抑えていた雇用保険料率を元に戻すことになったと見られています。
今回の引上げに至った具体的な原因としては、「雇用調整助成金の申請増加」と「失業手当の受給者の増加」があります。
○「雇用調整助成金の申請増加」
雇用調整助成金とは、経済的な事情により事業を縮小した事業者が、労働者の雇用を維持するために、一時休業等を行った場合に助成する制度です。2020年以降、新型コロナ対策として、雇用調整助成金の助成率および上限額を引き上げる特例措置が設けられていますが、長引く新型コロナの影響により、雇用調整助成金を申請する事業者が急増しました。
厚生労働省によると、2020年2月から2021年9月までの雇用調整助成金の支給決定件数は、441万2511件、4兆3481億円に上っており、リーマンショック後の4倍以上になっています。
雇用調整助成金の財源は、企業と労働者が負担する雇用保険料が基本となっているため、財源強化のために、雇用保険料率の引き上げが必要になっています。
○「失業手当の受給者の増加」
新型コロナによる失業者の増加も、雇用保険料率引き上げの大きな要因の1つです。
そもそも雇用保険の主な目的は、労働者が失業をした場合に必要な給付を行うことで、労働者の生活や雇用の安定を図ることにあります。
ニュース等で連日報道されているとおり、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、倒産や解雇等により失業してしまった方が多くいます。
その結果、失業給付等が増加したことが、雇用保険料率の増加につながっています。
- 雇用保険料の引上げで事業主・労働者にはどう影響する?
当然のことですが、雇用保険料率が引き上げられると、労使双方が負担する雇用保険料が増加します。
例えば、月の賃金が30万円の場合、労働者負担は900円から1,500円、企業負担は1,800円から2,550円まで増加。1か月あたり・1人あたりの金額はそう大きく感じないかもしれませんが、継続的に負担が増加したり従業員数が多かったりする企業の場合、労働者の負担も企業の負担も大きなものとなります。
また、雇用保険料率が引き上げられると、企業は雇用保険料の負担を避けるため、労働時間が週20時間未満のパートやアルバイトなど、雇用保険の加入義務のない短時間労働者を中心に採用する可能性があります。
労働者側としても、雇用保険料の負担が増えると給料の手取り額が減少してしまうため、非正規雇用を選ぶ労働者が増える可能性があるでしょう。

- まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は4月より引き上げられる雇用保険料率について説明しました。
個人的な意見にはなりますが、今回の料率増加の影響は、規模が大きい会社では大きいものの、労働者個人としては円安に基づく物価高に比べると、その影響は限定的であり、雇用保険料の値上げよりも食料費や光熱費の上昇の方に気を配る必要があると感じます。
ですが、給与計算や年度更新の際は注意が必要です。もしこれらの手続きに不安がある方、
社会保険に関すること、被扶養者の要件、手続きの方法、傷病手当金、出産手当金及び障害年金等でお困りの方は社労士が複数在籍している札幌・東京の社会保険労務士法人Aimパートナーズまでお気軽にお問い合わせください。
- ■前の記事へ
- 雇用契約書と労働条件通知書の違いについて
- ■次の記事へ
- 【話題】「今こそスノチャレ北海道」とは